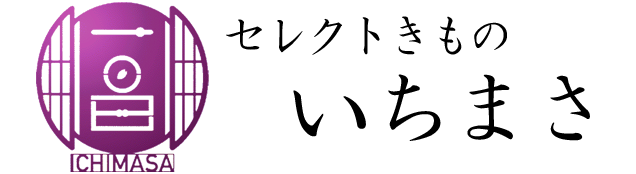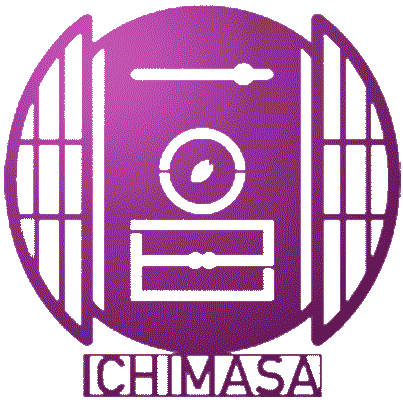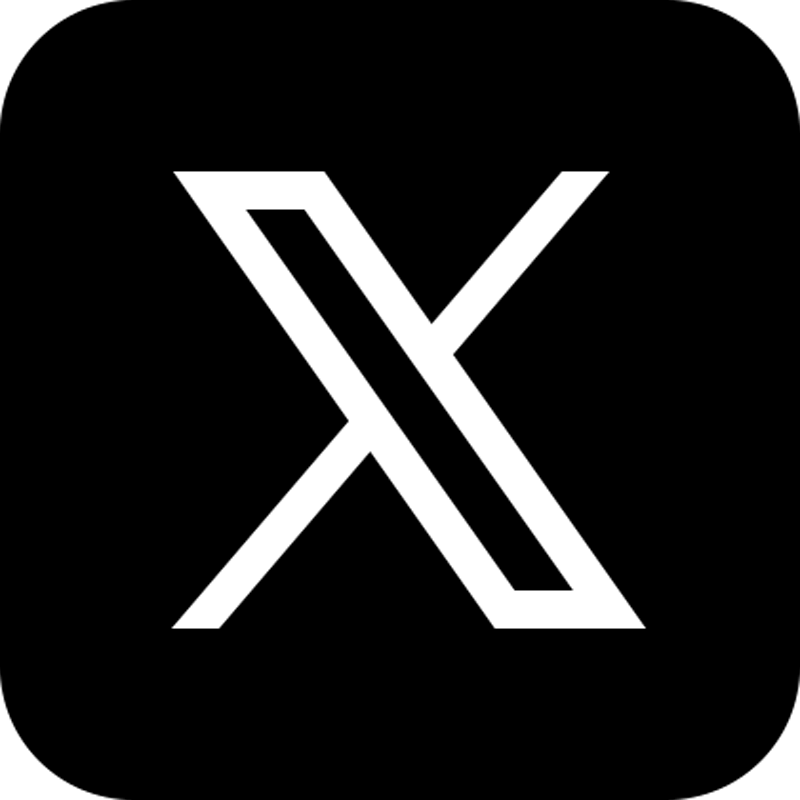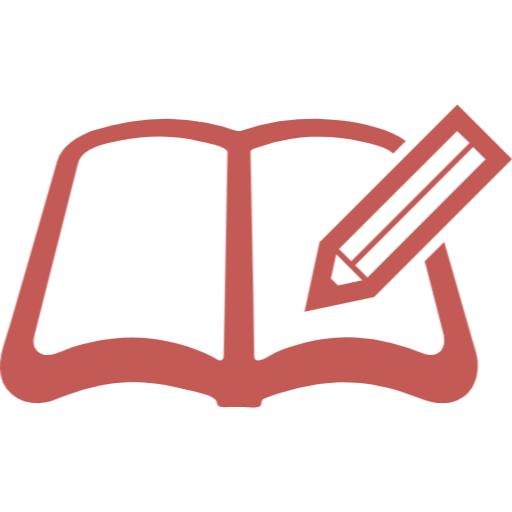単衣っていつから着るの?
単衣は胴裏や八掛などの裏地がつかないお着物のこと。本来は6月・9月といった袷と夏物の間に着る着物ですが、昨今の温暖化の影響で4〜5月、10月にも単衣を着る方が増えてまいりました。
訪問着や色無地などの染めのお着物を単衣に仕立ててフォーマルなお席に、紬、御召などの織りの着物でカジュアルにと、袷と同様のTPOでさらに気候に合わせた装いが実現できます。
気候に合わせ体調を第一に考えながらも、単衣を上手に取り入れて季節の変わり目を美しく装ってまいりたいものです。
【単衣仕立て】

一枚の生地を裏地なしで御仕立します。
身頃もお袖も一枚布です。腰の下から白い絹地を付けていますがこれは居敷当てと呼ばれる所です。
意図としては薄衣の為透け感の防止、縫い目の保護と言う観点で施される現代的な御仕立です。
暑さをしのぐと言う意味合いを重視すると特に付けなくてもよいものではございます。
身頃もお袖も一枚布です。腰の下から白い絹地を付けていますがこれは居敷当てと呼ばれる所です。
意図としては薄衣の為透け感の防止、縫い目の保護と言う観点で施される現代的な御仕立です。
暑さをしのぐと言う意味合いを重視すると特に付けなくてもよいものではございます。
【胴抜き単衣仕立て】

一枚の生地を八掛、袖口布、腰辺りの薄絹を付けて仕立ます。
背中、胸と言う帯が重なり汗がたまりやすい箇所の胴裏地を抜いて仕立てます。
現代の温暖化に伴い生み出された比較的新しい御仕立方法です。
初夏初秋の端境期となる4月後半〜5月半ば、9月後半〜10月末くらいではないでしょうか。
外観からは袷に見える御仕立ですのでフォーマルな場やお茶席など従来の単衣カレンダーに準ずることが望ましいとされる場面にも活躍します。
あくまで御地の気候に沿った装いをお勧めいたします。
背中、胸と言う帯が重なり汗がたまりやすい箇所の胴裏地を抜いて仕立てます。
現代の温暖化に伴い生み出された比較的新しい御仕立方法です。
初夏初秋の端境期となる4月後半〜5月半ば、9月後半〜10月末くらいではないでしょうか。
外観からは袷に見える御仕立ですのでフォーマルな場やお茶席など従来の単衣カレンダーに準ずることが望ましいとされる場面にも活躍します。
あくまで御地の気候に沿った装いをお勧めいたします。
【二重紗】

二枚の夏生地を重ねて御仕立します。
使用される生地は絽、紗となります。
下地に当たる部分に手描きや型染めで染文様を描きその上に更に紗生地を重ねてあえて文様を控えめに見せる贅沢で奥ゆかしい呉服の形です。
生産量が激減し店頭販売ではなかなか拝見する機会がない希少な二重紗です。
着用時期は単衣と全く同じです。
使用される生地は絽、紗となります。
下地に当たる部分に手描きや型染めで染文様を描きその上に更に紗生地を重ねてあえて文様を控えめに見せる贅沢で奥ゆかしい呉服の形です。
生産量が激減し店頭販売ではなかなか拝見する機会がない希少な二重紗です。
着用時期は単衣と全く同じです。
【盛夏の単衣】

一枚の生地を裏地なしで御仕立します。
素材は紗、絽、羅、紗紬、綿、麻などを用います。
日本が一番暑いとされる7月8月の衣です。
湿度の高い日本の夏を乗り切るために考慮された衣です。
涼を求め透け素材を使用し空気を通し熱を逃がす役割を果たします。
注目すべきはこの盛夏の7月、8月の装いです。
気温が35℃を超える日は9月末頃まで続きます。
盛夏の衣を9月に入ってもお召いただくことにどうぞ抵抗なく令和の気候に配慮した装いをお勧めいたします。
素材は紗、絽、羅、紗紬、綿、麻などを用います。
日本が一番暑いとされる7月8月の衣です。
湿度の高い日本の夏を乗り切るために考慮された衣です。
涼を求め透け素材を使用し空気を通し熱を逃がす役割を果たします。
注目すべきはこの盛夏の7月、8月の装いです。
気温が35℃を超える日は9月末頃まで続きます。
盛夏の衣を9月に入ってもお召いただくことにどうぞ抵抗なく令和の気候に配慮した装いをお勧めいたします。
いかがでしたでしょうか。
単衣のお着物と呼ばれる中にもいくつかの御仕立方法、素材の考慮が見られます。
温暖化の進む中で単衣は益々必要性を増しています。
昔の着物ルールでは乗りきれない事は皆様にもお感じかと思います。
どうぞ気候を優先し教科書に捕らわれない健康的な装いをご提案したいと思います。