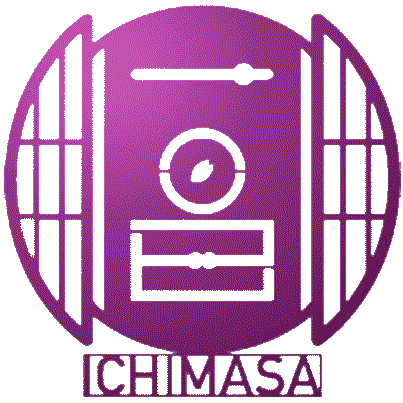今日は個人的にも大好きな”綴れ織り”についてちょっと書いています^^



正装、礼装以外は使えない?と思われている綴れ織りですが実はとんでもない誤解です。
特に八寸は日常使いにドンドンお召いただきたい丈夫で日本的センスあふれる名古屋帯ではないでしょうか。
なかなか見かけない国産の綴織、爪掻本綴織は現在では生産数がきわめて少なく常時店頭に並べて販売されることはほぼございません。
ですのでその感触も風合い、締め心地も実際に知る機会がなくなりつつあります。
伝統的工芸品産業の法律により指定されている西陣織は12種類存在します。
各種の技法は異なり、1.綴 2.経錦 3.緯錦 4.緞子 5.朱珍 6.紹巴 7.風通 8.綟り織 9.本しぼ織 10.ビロード 11.絣織 12.紬 の12種類。
綴れ織りは経糸が表面に出ないためスッキリとした締め心地が味わえるわけですね。
当然ですが裏側も同じ柄が出来上がります。
手技と色糸の美しさが奏でる芸術的な染織です。
現代人が本当に知らない職人さんたちの日々のご努力が1本の帯になって示されています。
柄や色が先行して生やされる現代ですが本当に日本が持つ美術工芸の素晴らしさを忘れている気がしてなりません。
売れる売れないの経済状況だけで日本の呉服、着物と言う文化が大きく変貌していくことが怖くなることがあります。
綴れ織りは1本約4m強の長さがあり杼を交換しながら一本の糸を整え打ち込む回数は2万4000回とも言われます。
同じ調子で打ち込込み続けなければ柄がゆがんだり帯地の厚みにムラができたりと綺麗に織りあがらないそうです。
2万4000回を毎日毎日同じ調子で織り上げていく精神力はいかほどでしょうか。
私なんて到底できない作業です。暑い日も寒い日も、嬉しい日も悲しい日も「パタン・パタン・パタン」と均一な神経をもち織り続ける。
気が遠くなるような職人技がなぜもっと評価されないのかと残念になりますね。
今回のピックアップは是非、我が国の伝統工芸をご覧頂きたいという思いでご紹介しています。
これだけの作業と修練の賜物、高い安いの判断はどこなんでしょうか?
伝統工芸を支える職人さんの仕事をどうぞ知っていただきたいと思います。
是非、商品説明内にも文面がございますので御覧ください。
沢山の思いを込めたピックアップでした。
春が待ち遠しいですね。ご一緒に綺麗を楽しみましょう。
https://ichimasa.shop-pro.jp/?mode=srh&sort=n&keyword=3387-
伊藤昌子