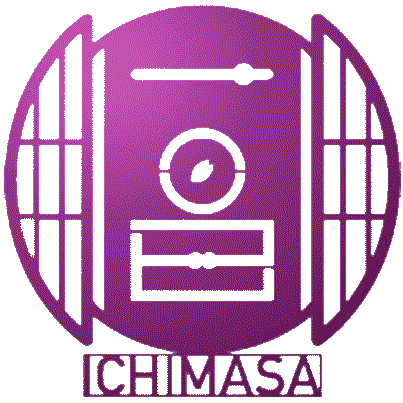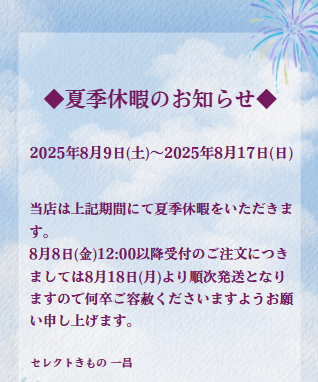日本の夏の風物詩の一つ「花火」。
毎年夏のイベントとして楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。
「風流な伝統文化」としてすっかり日本に根付いている花火ですが、そのルーツは古代中国で軍事用として使われていた狼煙(のろし)だったと言われています。薬を作っていた錬丹術師によって偶然生み出された火薬は当時武器や狼煙に使われていましたが、13世紀後期ヨーロッパ諸国に伝わると貴族のお祝い事などの「祝砲」にも使われるようになり、これが現在の「打ち上げ花火」の原型となったと言われています。
日本にその火薬が伝わったのは鎌倉時代(文永11年)の蒙古軍襲来の頃とも室町時代(天文12年)の鉄砲伝来の頃とも言われ諸説ありますが、やはり武器用として持ち込まれたものだったそうです。観賞用花火に使われるようになったのは戦乱の世が終わった江戸時代のこと。あの徳川家康が日本で初めて花火観賞を楽しみ、八代将軍吉宗は当時起きた大飢饉による死者の慰霊と悪疫退散のために花火を打ち上げました。これが東京の「隅田川花火大会」の始まりだったと言われています。
もとは武器用として持ち込まれた火薬が、やがてはこうして人々の目を楽しませ、魂を癒し、疫病退散や安寧の世への願いを込めて打ち上げられる花火に使われるようになったことを思うと、特別な思いが込み上げてきます。そして気がつけば世界に誇れるほどの精巧さと美しさを備え、今もなお進化を続ける日本の花火はまさに職人たちの繊細な感性と高い技術、そしてたゆまぬ努力の賜物といえますね。この夏もこの美しい日本の花火が観られることをあらためて本当にありがたいことだと感じます。
皆さまもこの夏花火を楽しまれていますでしょうか。花火大会へのお出かけはもちろん、浴衣で手持ち花火を楽しみながら夕涼みをするというのも素敵ですね。
皆さまが素敵な夏のひとときを過ごされますように。
文章:一昌スタッフ・塚本