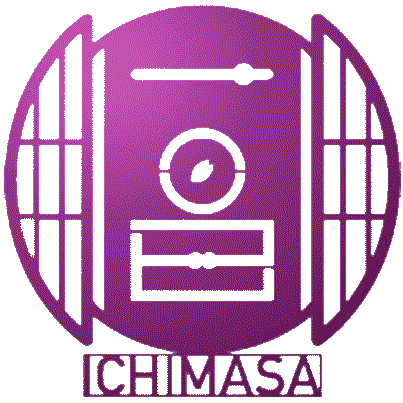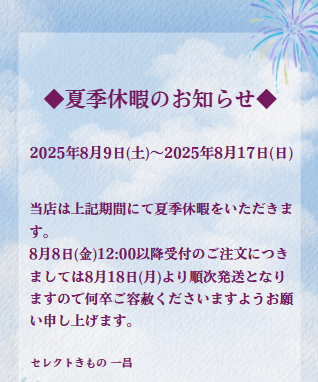新緑が目に眩しく、爽やかな風が感じられる季節になりましたね。
今回のテーマは「葵祭」。

毎年5月に上賀茂神社と下鴨神社で執り行われる五穀豊穣を祈る例祭で「祇園祭」、「時代祭」と並ぶ京都三大祭のひとつとしても知られています。正式には「賀茂祭」 と呼ばれ1500年も前から親しまれてきたという長い歴史がある例祭です。
5月に入り「流鏑馬神事(やぶさめしんじ)」を皮切りに「賀茂競馬(かもくらべうま)」など有名な儀式が続きますが、葵祭のハイライトといえば「路頭(ろとう)の儀」と呼ばれる神事の勅使による大行列。平安装束をまとった総勢約500人もの人々が行列をなし、馬や牛車などとともに京都御所から下鴨神社、そして上賀茂神社へと向かいます。この大行列がテレビなどでもよく紹介される葵祭の代表的な光景です。
「本列」で勅使の役割を務める近衛使代(このえつかいだい)がこの行列の主役ではありますが、その華やかさで毎年特に注目が集まるのは本列に続く「斎王代列」ではないでしょうか。「斎王代」というのは、平安時代に天皇の皇女や皇室の未婚の女性の中から選ばれて賀茂社に奉仕した「斎王」のその代わりをつとめる女性のこと。現代では毎年葵祭の時期に京都にゆかりのある女性が選ばれ、十二単を纏った華やかな姿でその勤めを果たすのですが、その斎王代を中心とした女人列の美しい平安装束に注目してみるのも素敵な楽しみ方の一つかと思います。
葵祭の装束はすべて装束司により有職故実に基づいて作られたもの。美しい「かさね色目」を楽しんだり、青海波、花菱、亀甲、華紋など、長い年月を経ていまもなお愛される古典文様を見つけては、はるか昔の平安の世に思いを馳せ心ときめかせてみてはいかがでしょうか。

有限会社 一昌 セレクトきもの一昌