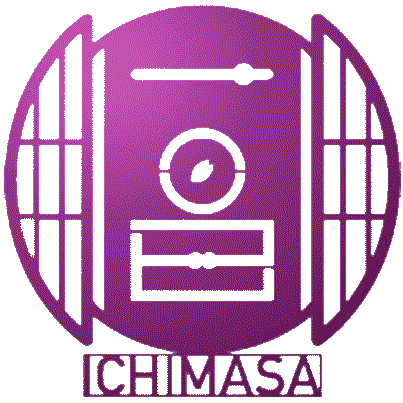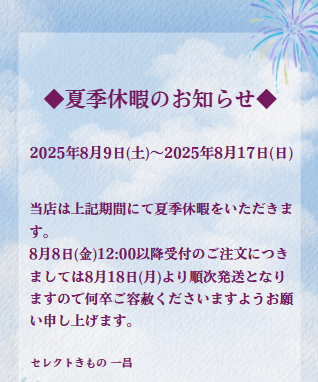木々の葉も美しく染まり始め、秋の深まりを感じる頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
今月のテーマは「亥の子」 。これは主に西日本で見られる伝統行事の一つで、無病息災・家内安全や多産の猪にあやかり子孫繁栄を祈る催しのこと。平安時代に中国から伝わったもので「亥の月(旧暦10月)の亥の日、亥の刻に餅を食べると病にかからない」と考えられた中国の民間信仰が起源と言われています。

日本の伝統行事では「亥の子餅」を食べたり「亥の子突き」が行われたりします。「亥の子餅」は亥の子の日に無病息災を願い食べる行事食。11月になると、地域の和菓子店にはイノシシの形やうり坊のような縞模様が付けられた餅菓子が並びます。一部の農村地域で行われる「亥の子突き」は、地域の子供たちが亥の子唄(囃子歌)を歌いながら家の前の地面を藁束や大きな石などで叩いて家々を回るという催しのこと。収穫の祝いと神への感謝を込め地面を叩くことで、邪気を祓いネズミやモグラなどの害獣を追い払うと言われています。子供たちはそのご褒美として亥の子餅やお菓子、ご祝儀などをもらえるのだそうです。
こういった伝統行事は時代背景や様々な社会的諸事情により年々取りやめとなっていくものも多くあり、亥の子もまたその一つかもしれません。それでも一部地域で「亥の子突き」を復活させたり、京都の護王神社(ごおうじんじゃ)では平安時代の宮中儀式を再現した「亥子祭」が今でも行われていたりと、伝統を継承しようとする動きがあることもまた事実です。茶道の世界でも亥の子に炉開きが行われる地域があり、これは中国の陰陽五行説で「水性」にあたる“亥”が火災除けとなる縁起担ぎなのだそうですが、ここでお茶菓子として亥の子餅が振る舞われると、人々の「無病息災」の願いをのせたその愛らしい姿にちょっとしたときめきを感じたりもします。
木枯らしが吹く季節ももうすぐやってまいりますね。この季節も皆様が健やかにお過ごしになれますように。
文章:一昌スタッフ・塚本